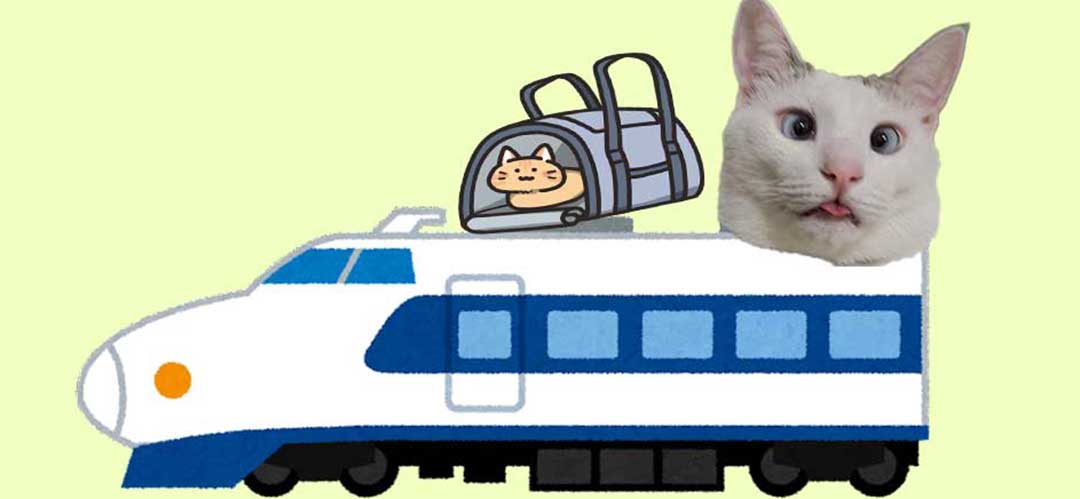「ウソみたいな!進化論の話(2)ダーウィン以後」
「ウソみたいな!?進化論の話(1)?ダーウィン以前?」の続きです。
前回は、生物学者・池田清彦さんのお話をもとに、ダーウィン以前の進化説についてみてきました。後半である今回は、ダーウィンが進化論を唱えた19世紀から、20世紀以降それがどう展開していくかを追っていきます。
最初に池田さんの結論を先取りすると、「(ネオダーウィニズム的な意味での)進化はない」というのがそれです。ネオダーウィニズムとは、ダーウィンの自然選択説にメンデルの遺伝学が加わった、現代版の進化論です。つまり、「現代的進化論のいう意味での進化に反対」ということですが、これだけだとまだよくわかりません。
そこでまず、ダーウィンの進化論からみていきましょう。
1859年、ダーウィンの『種の起原』が刊行されます。
彼はそのなかで、
(1)「自然選択による進化」
(2)「種の分岐(分化)」
という考えを提唱しました。
ダーウィンがこうした考えを主張したのは、生物の多様性を説明するためです。その点は、前回登場したラマルクと同じです。つまり、最初から進化それ自体を主張したかったわけではないということに注意してください。
(1)「自然選択による進化」とは次のような考えです。
生物は生活環境が変わると「変異」を起こすことがあり、その一部は遺伝します。「変異」とは、例えば毛が生えたり、色が変わったりすることです。環境に適した変異は残りやすく、結果として、その生物の種全体に広がります。そして、ひいては生物全体が少しずつ適応的なものに変化していきます。
こうした考えの前提には、生存率の低さという一般的な事実があります。例えば、マンボウは一回の産卵で約1億5千万の卵を産むと言われますが、そのなかで成長して親になれるのは基本的に1匹しかいません。つまり、当然ですが、生物の数は有限であるということです。
そのため、ある変異をもった生物の数が急激にまたは徐々に増減したり、時には絶滅してしまったりすることは生物の宿命でさえあると言えるでしょう。自然選択のプロセスは、こうした事態にますます拍車をかけるのです。
この延長線上に、(2)「種の分岐」という考えが出てきます。
ある生物の種は進化の過程で複数の種に分岐していくという考えです。これは裏を返せば、現在の生物にみられる多様性は幾世代もの分岐の結果であるというわけです。そして、現在の多様な生物も、もとをたどれば少数の共通した祖先にさかのぼることができる。ダーウィンはそう考えました。
同じ19世紀に、メンデルが遺伝の法則を発見します。彼はエンドウマメの交配実験によって、背が高いとか低いとかいった形質が遺伝する法則を明らかにしました。
ただし、遺伝という現象自体は当時一般に信じられており、ダーウィンもメンデルとは独立に、遺伝現象があることを認めていました。
20世紀に入り、1940年代になると、ダーウィンとメンデルの学説をもとにしたネオダーウィニズムが確立されます。これは、最初から「進化」の原因を説明しようとしている点では、ラマルクやダーウィンの進化論とは異なります。
ネオダーウィニズムは、進化の主原因を「突然変異に自然選択が働くこと」であるといいます。ダーウィンが「変異の一部は遺伝する」と考えたのと同様、ネオダーウィニズムも、遺伝の際に自然選択が働き、環境に適した遺伝子が時間の経過とともに特定の種のなかに固定されると考えるのです。
これに対して1980年代以降、池田清彦さんらが構造主義生物学の立場から反論を始めます。
池田さんによれば、そもそも自然選択の実証例はそう多くありません。そのため、突然変異で生まれた何らかの性質が環境に適しているかどうかは一概に決められないのです。つまり、自然選択はあくまで進化の一要因(マイナーなプロセス)であって、主原因とは言いがたい。
これが、冒頭で述べた「(ネオダーウィニズム的な意味での)進化はない」ということの真相です。
また自説の根拠として、池田さんは次のような遺伝のメカニズムを説明してくれました。
人間の遺伝子は約2万2千あり、すべての細胞のなかには同じ遺伝子が入っています。そこで個々人に違いが生じるポイントとなるのは、「どの遺伝子がどのタイミングで発現するか」なのだそうです。ここで「発現する」とは、単純に「スイッチが入る」ことであると考えてください。
遺伝子にスイッチが入ると、細胞内でタンパク質が作られ形質が決定します。逆に、スイッチが入らなければ、遺伝子はうまく機能しません。しかし、スイッチが入るかどうかは、かなりの程度偶然によって決まるのだそうです。
つまり、自然選択はあくまで結果論であって、必然的なプロセスではないということです。
以上が池田さんの主張の骨子です。私には日頃なじみのないテーマなので、メモを取るだけで精一杯でした。
その日の最後に、池田さんは次のようなお話をしてくれました。とても象徴的な例だと思います。
クジラのDNAに一番近いのは、実はカバのDNAであると言われます(DNA≒遺伝子)。
今から約5000万年前、太古のクジラにはカバと同じように足があり、地上を歩いていました。
ところが、あるとき突然、クジラの遺伝子にシステム上の変化が起こり(≒スイッチが入り)、足がなくなってしまったのです。
そこで足を失ったクジラは、陸上を捨て、海に移ります。しかし、陸上に住み慣れた生物が足を失ってまで海で暮らすようになるという事態は、ちょっと説明がつきません。
池田さんは、どういうわけか先に形が変わり出したのであって、環境に適応したわけではないと言います。
確かに、そうかもしれません。でも、だとすれば、人間だって今まで働いていなかった遺伝子に突然スイッチが入ったら、将来何になるか知れたものではないわけです。
そう考えると、期待と不安が入り混じったような気分になって、私は生命の奥深さをあらためて実感してしまうのでした。
 |
| ダーウィンを描いた風刺画(1871年の雑誌に掲載) |